ZEH・LCCM住宅の推進に向けた取組とは?それぞれの違いや適用補助金の条件を解説【2030・2050年目標】
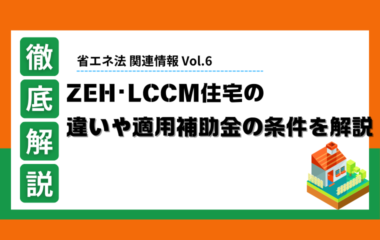
現在、国土交通省では「ZEH」「LCCM住宅」を増やすため、さまざまな制度を立ち上げ、支援提供に力を入れています。では、2つの建物にはどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、ZEH・LCCM住宅の概要を解説したのちに、2つの要素の違いや建築するメリット、適用できる補助金について詳しく説明します。
目次
ZEHとは
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)は、次のような対策を講じられた建築物を建てることにより、年間の一次エネルギー消費量の収支をゼロにすることを目指す住宅です。
- 高断熱性能(外壁や窓の断熱性能を向上させて冷暖房効率を高める)
- 高効率設備(省エネ型の空調・給湯・照明設備を採用してエネルギー消費を削減)再生可能エネルギー導入(太陽光発電システム等を設置して消費電力をまかなう)
経済産業省では「第6次エネルギー基本計画(2021年10月閣議決定)」のもと、2030年までに新築住宅をZEH化することを目標とされています。
LCCM住宅
LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)住宅は、以下に示すすべてのライフサイクルにおいて、CO2排出量を削減し、最終的にはCO2の収支をマイナスにすることを目指す住宅です。
- 建設時(建築時)
- 居住時
- 廃棄時
例えば、建材の製造から建設、居住、解体・廃棄に至るまで、各段階でのCO2排出を最小限に抑えるほか、居住時には太陽光発電を活用して、エネルギーの自給自足を図ります。また、耐久性の高い材料や設計を採用することで、住宅の寿命を延ばし、住宅の材料を廃棄処分することで発生する環境負荷を低減することが可能です。
なおLCCM住宅は、国土交通省より「脱炭素型先導住宅」と位置付けられており、環境性能の最高ランクとして普及が進められています。またLCCM住宅については、2050年に主流化することが目標として掲げられている状況です。
ZEHとLCCM住宅の違い
似た建物の構造であるZEHとLCCM住宅には、次の違いがあります。
| ZEH | LCCM住宅 | |
| エネルギー収支の目標 | 年間の一次エネルギー消費量をゼロにする | ライフサイクル全体でCO2の収支をマイナスにする |
| 対象範囲 | 居住時のエネルギー消費と再生可能エネルギーの創出 | 建設、居住、廃棄の全ライフサイクル |
| 再生可能エネルギー | 主に太陽光発電の導入で対応 | 太陽光発電に加え、建材や設計の工夫でCO2を削減 |
| 目標年 | ・2030年に原則ZEH化 | ・2030年にZEHの上位モデルとして一部普及 ・2050年に主流化 |
ZEH・LCCM住宅に共通するメリット
ZEHとLCCM住宅は、それぞれ技術的な違いはあるものの「これからの時代に適した住宅」として共通するメリットがあります。
ここでは、代表的なメリットをポイントごとにまとめました。
省エネ性能で資産価値をキープ(将来性)
ZEHやLCCM住宅は、日本が取り組んでいる「脱炭素政策」と連動していることから、将来的に日本の住宅の標準仕様になる可能性が高いです。
高い省エネ性能や再生可能エネルギーの導入は、将来の住宅市場において資産価値を維持する大きな要因となります。それに加え、電力料金の高騰やエネルギーの不安定化が続くなかでエネルギー自給率を維持できるため、ライフライン費用の削減に貢献できるのが魅力です。
再エネ賦課金といった、費用増になる要因を回避しやすくなることから、人々の豊かな暮らしに役立つ住まいのかたちだと言えるでしょう。
一年中住みやすい温熱環境(快適性)
ZEH・LCCM住宅は、いずれも高断熱・高気密を基本としているため、外気の影響を受けにくく、室温を一定に保ちやすい構造が特徴です。
その効果もあり、少ない電力消費だけで「夏は涼しく冬は暖かい環境」を維持できます。また寒暖差を抑えられることから、ヒートショック・熱中症といった健康面のリスクを軽減できるのがメリットです。
ノンストレスで過ごせる家づくりに欠かせない構造ですので、安全かつ快適な生活に必須の家のかたちだと言えるでしょう。
地球温暖化防止に貢献(環境性)
ZEHやLCCM住宅は、ただ私たちの住環境を快適にするだけではなく、地球環境にもメリットを生み出します。
まずふたつの住宅は、ともにCO2排出量を大幅に削減できる設計です。従来の家と比べて電力消費量を抑えやすいことから環境配慮型の住まいとして評価されています。
またZEHは居住時の「エネルギー収支ゼロ」、LCCM住宅は「ライフサイクル全体でのCO2マイナス」を目指しているため、地球温暖化防止に貢献できるのがメリットです。1世帯の取り組みが社会全体の脱炭素化にもつながる点が、今後大きな価値となっていくでしょう。
ZEH・LCCM住宅に共通するデメリット
生活やライフラインコスト、そして環境に優しいZEH、LCCM住宅ですが、3つのデメリットに注意しなければなりません。
初期費用が高くなる傾向がある
ZEHやLCCM住宅を建てる際には、次のような設備導入に高額な費用がかかります。
- 断熱材
- サッシ
- 省エネ機器
- 太陽光発電
高性能な材料が求められることから、一般的な住宅と比べて初期コストが100万〜300万円程度高くなる場合があります。後述する補助金制度を活用すれば費用負担を抑えらるものの、若干の手出しが出てしまう点に気を付けてください。
設計や施工に専門性が求められる
ZEH・LCCM住宅のように「高い省エネ性能」をもつ家を建てるためには、建物の構造や設備配置まで含めた専門的な設計が必要になります。
また、性能を発揮させるためには施工の精度や断熱処理の技術力も重要であることから、対応できる設計事務所や工務店が一部に限られてしまう点に気を付けなければなりません。
なお、原則ZEH化といった取り組みが実施されている現代では、ほとんどの業者がZEHに対応できています。たださらにランクが高いLCCM住宅については、まだ対応できる業者が限られている点に気を付けてください。
メンテナンスや機器更新コストがかかる
ZEHやLCCM住宅は初期導入費用だけではなく、次のような設備の維持管理に対してランニングコストがかかります。
- 太陽光発電
- 蓄電池
- 換気システム
定期的な点検はもちろん、将来的に更新費用が発生します。一般的に、太陽光パネルが20~30年程度、パワーコンディショナーが10〜20年で寿命を迎えるため、ランニングコストを含めた費用の理解が欠かせません。
ZEH・LCCM住宅で利用できる補助金
従来の家と比べて高性能な分、高額になりやすいZEH・LCCM住宅に対し金銭的な課題を抱えている人も多いでしょう。それなら、次の補助金を活用するのがおすすめです。
| 補助金の名称 | 提供元 | 補助額 |
| こどもエコすまい支援事業 | 国土交通省 | 100万円/戸(新築注文住宅) |
| LCCM住宅整備推進事業 | 国土交通省 | (設計費+建設工事等における補助対象工事の掛かり増し費用)×1/2 |
| 家庭用蓄電システム補助金 | 経済産業省 | ・3.7万円/kWh(初期実行容量)・補助率1/3以内、上限60万円 |
| こどもみらい住宅支援事業 | 国土交通省 | 100万円/戸 |
| 戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業 | 環境省 | 55万円/戸 |
なお補助金は、年度によって提供のタイミング、継続状況が変化します。申請をする際には、事前に最新の補助金を利用できるか確認しましょう。
まとめ
ZEH・LCCM住宅は、それぞれ2030年を目標として建築が推進されている建物であり、特にZEHについては、2030年に原則ZEH化が目標とされています。また2050年にはLCCM住宅が標準になるように動き出しているなど、今後の家づくりに欠かせない要素です。
建物の構造によって利用できる補助金、そして住宅ローン控除の条件なども変化するため、家を建てる際にはどの構造の家を建てるのが自分にとってベストなのかを検討することが欠かせません。

