二地域居住とは|メリット・デメリットや国交省補助金事例

目次
トレンドワード:二地域居住
「二地域居住」についてピックアップします。都市と地方、2つの地域に生活拠点を持つ「二地域居住」は、テレワークや多拠点生活の広がりとともに注目を集めています。2024年には法改正も行われ、国や自治体も制度的な支援を強化中です。本記事では制度の概要やスタイル別の特徴、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。
二地域居住とは
ここではまず、二地域居住の概要や法律関連の動きについて解説します。
二地域居住の概要
二地域居住とは複数の生活拠点を持ち、定期的に移動して生活や仕事をするライフスタイルです。完全移住よりハードルが低く、「関係人口」の拡大を通じて地方の活性化を図ります。
地方では新たな担い手や消費が生まれ、都市では自然や文化を享受できるなど、双方にメリットがあるのが特徴です。ただし住まいや仕事、コミュニティへの参加といった課題への対策が十分でないとの指摘もあります。
「広域的地域活性化基盤整備法」が改正
「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」が、2024年に施行されました。主な改正内容は、下記3点です。
- ①【都道府県・市町村の連携】二地域居住促進のための市町村計画制度の創設
- ②【官民の連携】二地域居住者に「住まい」・「なりわい」・「コミュニティ」を提供する活動に取り組む法人の指定制度の創設
- ③【関係者の連携】二地域居住促進のための協議会制度の創設
従来の県による計画に加え、市町村が主体で「特定居住促進計画」を策定可能になった点が変更されています。
さらに支援法人の指定や協議会制度創設のほか、空き家の改修やコワーキング整備への法的特例措置などにより、地方への人流創出を強力に後押しします。
【参考】e-GOV|広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第三十一号)
二地域居住スタイルの種類

ここでは、二地域居住スタイルの種類について解説します。
二地域就労型
二地域就労型は都市部と地方の両方で仕事をするスタイルで、リモートワークの普及により近年注目が高まっています。平日は都市部の会社に出社しつつ、週の一部や一定期間を地方で過ごし、現地での副業やテレワークに取り組むケースも増加しています。
地方での人手不足解消やスキル移転にも貢献できる働き方として期待されており、柔軟なライフスタイルの実現手段として有効です。
別荘・セカンドハウス型
別荘・セカンドハウス型は、地方に別荘やセカンドハウスを所有して季節や気分に応じて滞在するスタイルです。仕事の拠点は都市部にある場合が多く、自然豊かな環境でのリフレッシュや趣味活動を目的に利用されます。
生活の質を高める「余暇重視型」のライフスタイルで、リタイア層や高所得層に多い傾向があります。ただし、維持管理や固定資産税などのコスト負担が課題です。
週末滞在型
週末滞在型は、平日は都市部で働き、週末に地方の自宅や宿泊施設に滞在するスタイルです。短期間ながら定期的に地域との接点を持てるため、「関係人口」として地域活動に参加しやすく、移住前の試行としても人気があります。
交通アクセスの良いエリアでとくに広がりを見せており、地域とのゆるやかな関係づくりや自然との共生を求める場合に向いています。
二地域居住のメリット

ここでは、二地域居住のメリットについて解説します。
多様なライフスタイルに対応できる
二地域居住は都市の利便性と地方の自然環境の両方を享受できるため、個々の価値観やライフステージに応じた柔軟な暮らし方が可能です。具体的には平日に都市で働き、週末は自然の中で過ごすなど、働き方や趣味、子育て、介護といった生活ニーズに合わせた選択ができます。
フルリモートや副業制度の拡充により、こうしたスタイルが現実的な選択肢として定着しつつあります。
所属コミュニティの幅が広がる
都市と地方の両方で生活することで、それぞれに友人や知人、地域とのつながりが生まれ、多様な人間関係を築けます。新たな土地での交流を通じて視野が広がり、地域活動やボランティアに参加することで自己実現や社会貢献の機会も増加します。
これにより孤立を防ぎ、多拠点による心理的安心感を得られる点も魅力です。とくにリタイア後や子育て世代にとって、大きなメリットとされています。
災害リスクの軽減
都市部に災害が発生した場合でも、地方に別の生活拠点があることで避難先や物資確保の手段となり、生活の継続性を確保しやすくなります。とくに地震や水害などのリスクが高まる中、リスク分散の観点からも注目されています。
また地方での生活経験があることで、いざという時に柔軟な判断や対応がしやすくなるのもメリットの一つです。
二地域居住のデメリット
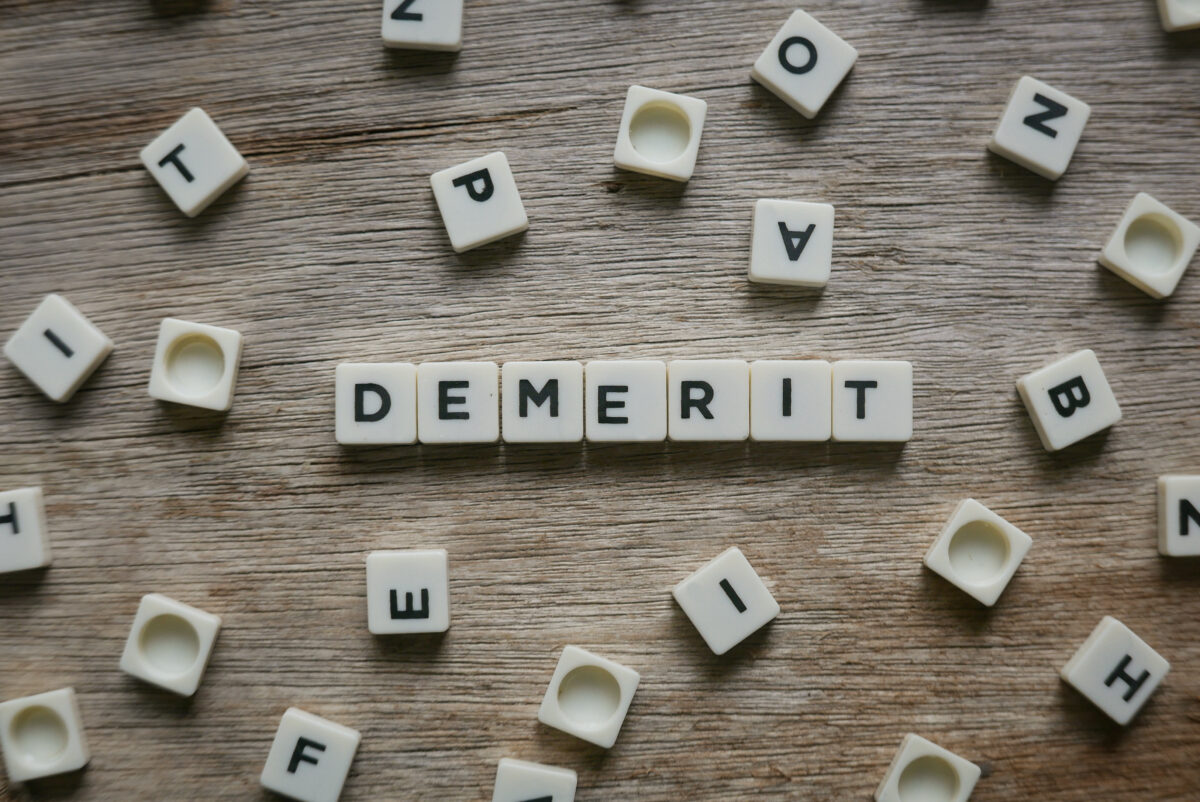
二地域居住にはメリットが多くありますが、いくつかのデメリットも存在します。注意点を知ることで、住宅計画・提案に活かしてみてください。
移住コストが掛かる
二地域居住では住宅の取得・賃貸・改修費に加え、水道光熱費や通信費、固定資産税など、生活拠点を2カ所持つことによるコストが発生します。空き家を活用する場合でもリフォーム費用がかさむケースが多く、初期費用の見積もりと長期的な維持費の把握が不可欠です。
金銭的負担が大きいため、資金計画をしっかり立てることが成功のカギとなります。
移動時間が負担になる
都市と地方を行き来する生活では、移動にかかる時間や交通費が生活の負担になることがあります。とくに交通機関の本数が限られる地域や、通勤・通学の必要がある場合はストレスや疲労の原因にもなります。
さらに天候や交通事情による影響も受けやすく、時間的余裕や柔軟なスケジュール調整が必要です。このように、移動の利便性も居住先選びの重要なポイントです。
住民票・住民税の手続きが必要な場合も
原則として住民票は1カ所にしか置けないため、生活の実態に合わせて主たる居住地を明確にする必要があります。住民票の所在により、選挙権や健康保険、住民税の課税先が変わるので、自治体によっては事前の相談や届出が求められることもあります。
二地域間での生活比率や滞在期間によって制度の適用が異なることから、事前の情報収集と手続きの確認が重要です。
二地域居住の事例|自治体支援・モデル事業
ここでは、二地域居住の事例をご紹介します。自治体によるモデル事業のため、幅広い地域に役立てられることが期待されています。
二地域居住の事例①北海道 上士幌町
北海道 上士幌町では、農村・中山間地域でも実現可能なスマートタウンの実装を目指して下記の取り組みを実施しています。
- 1)域内DXの推進
- 2)住民MaaS、ワーケーションMaaSの実装
- 3)域外からの企業・関係人口の取り込み
とくに二地域居住については、ビジネスホテルと連携して移動をセットにしたワーケーションパック(移動・宿泊・仕事サブスクモデル)の開発が注目されています。
二地域居住の事例②栃木県 小山市
栃木県小山市には新幹線の停車駅があり、「都心まで約40分」という強みを活かした取り組みを実施しています。具体的には空き家の活用・市のまちづくり参画などを通して、関係人口の増加を目指しているのが特徴です。
具体的には、二地域居住PRのために下記の取り組みを実施しています。
- 二地域居住をした場合、小山市と他市との比較ができるアプリ等の開発
- 週末体験モデル計画策定
- デジタルサイネージ設置等(ニーズ調査を元に効果が得られる場所、首都圏の駅又は小山駅)
- 二地域居を考えている人に向けた小山市及び市内物件紹介HP作成、運営、保守
- 週末体験コンテンツの実施、撮影(動画・写真等)
二地域居住の補助金・施策事例|国土交通省の支援
国土交通省では、二地域居住を推進するために様々な取り組みを実施しています。ここでは、二地域居住に関する補助金や施策の事例をご紹介します。
①情報提供
コロナ禍を経て、若者や子育て世帯を中心に地方回帰の気運・関心が高まっています。しかしニーズに沿った住まいが不足していたり、コミュニティ形成上の問題が生じたりするといったトラブルが課題です。
そのため国土交通省では先導的な事例を形成し、横展開を図る実証調査を実施しています。異なる分野等について補完できる内容とするなど、モデル事例の充実を図っている段階です。
②住まい
フラット35とは民間金融機関の全期間固定金利の住宅ローンで、新築住宅購入等で幅広く活用されています。さらに省エネ性・耐震性などの質の高い住宅を対象とした住宅ローン(フラット35S)や、子育て支援や空き家活用などの地方公共団体の施策と連携した住宅ローン(フラット35地域連携型)については、金利の引下げが実施されています。
取得者が自ら利用するセカンドハウスを取得する場合にも利用可能なので、二地域居住におすすめです。
さらに国土交通省では、市区町村が実施する空き家の除却・活用に係る取組や、NPOや民間事業者等が行う空き家の活用・改修工事等も支援しています。各自治体が把握・提供している空き家等の情報について、自治体を横断して簡単に検索できるよう「全国版空き家・空き地バンク」を構築することで、活用を促しています。
③テレワーク
テレワークが普及して場所にとらわれない働き方が定着しつつある中、新しい働き方・住まい方への対応が求められています。そこで国土交通省では、下記の補助金事業を実施しています。
- 地方移住促進テレワーク拠点施設整備支援事業
- 都市構造再編集中支援事業
- 都市再生整備計画事業
これによりテレワーク拠点等を整備し、職住が近接・一体となった柔軟な働き方等に対応したまちづくりを推進しています。
さらに「テレワーク人口実態調査」を実施し、テレワーク人口やテレワーカーの地域性等を把握・公表しています。2023年度の調査結果では、雇用型テレワーカーの割合は全国で24.8%でした。テレワーカーの割合は減少したものの、ハイブリッドワークが拡大しているのが現状です。
④観光
これまで横ばい傾向だった国内旅行市場が需要拡大へ転じるためには、新たな交流市場の創出が重要です。そのためには「何度も地域に通う旅、帰る旅」という新たな旅のスタイルで反復継続した来訪を促進する「第2のふるさとづくり」、コロナ禍を経たテレワークの普及や働き方の多様化を踏まえた「ワーケーションの普及・定着」等が有効と考えられます。
これにより旅の潜在需要を顕在化させ、地域の関係人口拡大にもつながる形で交流需要の拡大を図ることが求められています。
⑤地域交通
国土交通省では、デジタルを活用して交通とそれ以外のサービスをワンストップで提供する「日本版MaaSの推進」を支援しています。データの連携・利活用等により、地域が抱える様々な課題の解決に取り組んでいるのが特徴です。
さらに地域公共交通のリ・デザインを推進するため、モビリティ人材(地域交通と他分野の連携を推進するコーディネート人材、地域交通のマネジメント人材、デジタル活用等により地域交通を支援する人材など)の育成に関する仕組みの構築や運営等の事業に対する支援も実施しています。
まとめ
二地域居住は、柔軟な働き方や豊かな生活を実現しつつ地方との新しい関係を築くライフスタイルとして広がっています。近年の法改正により制度的な支援も整い、より多くの人が挑戦しやすい環境が整いつつあります。
一方で費用や移動の負担、行政手続きなどの課題もあるため、自身の目的や生活環境に合わせた検討が不可欠です。自分らしい暮らしを模索する選択肢の一つとして、今後ますます注目されるでしょう。

