【2025年4月施行】もうすぐ木造建築物の構造基準が見直されます!国土交通省発表の変更点をわかりやすく解説
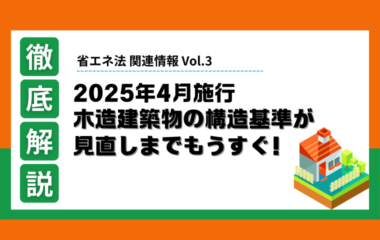
2025年4月、国土交通省より「小規模の木造住宅・建築物の構造基準」が見直される予定です。では、複数ある構造基準のうち何が変更されるのでしょうか。
この記事では、2025年4月最新の構造基準の見直しポイントについて説明したのち、具体的な変更点や改正の背景を紹介します。
目次
そもそも構造基準とは?
構造基準は、住宅や建築物の構造(部材の太さや耐力、安全性など)について設定されているルールのことです。日本で建築する建物の安全性を維持するため、建築設計者は構造基準に準じた住宅や建築物をつくらなければなりません。
なお、ここでいう構造基準とは、国土交通省が定めている「建築基準法施行令」の内容を指します。資料のなかで設定されている項目を選択しなければならないほか、建物の安全性を確認するための構造計算等を実施します。
構造基準改正は小規模の木造住宅・建築物が対象
2025年4月に施行予定である構造基準の改正は、複数ある建物の構造のなかでも小規模な「木造住宅」「木造建築物」が対象です。以下に小規模に該当する条件をまとめました。
- 2階建て以下である
- 高さ16m以下・延べ面積300㎡(およそ90.8坪)以下である
特に日本の建築物の多くは木造であり、住宅だけを見れば全体の54.0%が木造で占められています。
出典:国土交通省「令和5年住宅・土地統計調査」
一軒家などの低層住宅の多くが木造でつくられていることから、住宅をメインに設計・施工している企業にとっては、今回の改正が大きく影響します。
企業実績として木造住宅・建築物の対応が多いという場合には、ぜひ後述する構造基準の見直しポイントの内容をチェックしてみてください。
2025年4月に施行予定の構造基準の見直しポイント
2025年の構造基準の見直しで改正されるポイントは、以下の2つです。
- 壁両基準の見直し
- 柱の小径基準の見直し
それぞれ計算手法や、省略できる条件などが変更されました。詳しい変更点を見ていきましょう。
壁量基準(第46条)の見直し
まず、2025年4月の改正により、建物が持つ耐震壁や構造耐力を指す壁量基準が見直されることとなりました。
なお今回の改正では「建築基準法の計算に基づく場合」「別の構造計算の方法で算出する場合」の2つのパターンにおいて変更が加えられています。
建築基準法の計算に基づく壁量計算
従来どおり建築基準法に定められている壁量計算を用いる場合、以下に示す2つの方法で計算が可能です。
- 計算式を用いて必要壁量を算定する
- 早見表を用いて壁量を確認する
まず計算式を用いる場合には、「階高」「床面積」「屋根・外壁の仕様」「太陽光発電等の有無」の条件より算出した値が、それぞれ必要壁量(自身や風圧力に耐えられるか)を上回っているかを計算します。
なお計算をする際には、独自で計算式を汲むことも可能ですが、公益財団法人 日本住宅・木材技術センターが提供している「壁量等の基準(令和7年施行)設計支援ツール」を利用することで、すばやく計算できます。
また上記の計算式を使わずに、早見表を利用して壁量の安全性を確認することも可能です。同じく公益財団法人 日本住宅・木材技術センターで公開されている早見表を利用できます。設計する住宅・建築物が早見表の条件に合うのかを確認することで、安全なのかを証明するのがよいでしょう。
建築基準法の計算に基づかない壁量計算
建築基準法に基づかず、独自の構造計算で住宅・建築物の安全性を証明できれば、その際には前述した計算式に基づく壁量計算をまとめて省略できます。
企業独自の設計システムの都合上、許容応力度計算・限界耐力計算などを算出する必要がある場合には、その方法を選ぶことも可能です。ただし、構造計算を必要としない場合には前述した計算式や早見表を活用するのがよいでしょう。
柱の小径基準(第43条)の見直し
2025年4月の改正では、柱の負担面積を決める「小径」の計算ルールが見直されました。
まず変更されたポイントとして、従来の「軽い屋根」「重い屋根」という区分による小径の計算がなくなります。そのなかで新しく計算をするときには「建築基準法の計算に基づく場合」「別の構造計算の方法で算出する場合」の2つのパターンについて気を付けなければなりません。
建築基準法の計算に基づく柱の小径の計算
建築基準法で定められている柱の小径の計算を用いる場合、以下に示す4つの方法で計算が可能です。
- 算定式と有効細長比から算定する
- 樹種等を選択後、算定式と有効細長比から算定する
- 柱の小径にあわせて柱の負担可能面積を算定する
- 早見表を用いて柱の小径を確認する
まず上3つの項目については、前述と同様に公益財団法人 日本住宅・木材技術センターが提供している「壁量等の基準(令和7年施行)設計支援ツール」を利用することで計算できます。設計した木造住宅・建築物の条件に合わせて項目を埋め、小径の値を算出してみてください。
また上記の計算式を使わずに、早見表から柱の小径を導き出すことも可能です。設計している建物の条件に近い早見表の項目をチェックし、安全であることを証明できれば、上記の計算を省略できます。
建築基準法の計算に基づかない柱の小径の計算
企業独自に柱の座屈計算などの構造計算を実施し、そのなかで安全性を確認できている場合には、前述した柱の小径の確認を省略できます。
設計のなかで座屈計算の必要があるときや、使い慣れている計算ソフトがあるときには、そのまま省略するのがおすすめです。ただし、座屈計算を単体で実施することに手間を感じているなら、前述した計算式による算定もしくは早見表を活用するのが良いでしょう。
2025年4月の構造基準改正が実施される背景
そもそもなぜ、2025年4月に構造基準が改正されるに至ったのか、その理由を知りたい人もいるでしょう。以下より、改正が行われる理由を解説します。
建築分野で木材利用が促進されている
環境対策の一環として実施されているカーボンニュートラルの取り組みですが、その対策のひとつに木材利用の促進があります。
木材は、ほかの建築資材と比べて、CO2といった温室効果ガスを排出しにくいのが特徴です。そのため現在は、環境対策効果を生み出せる木造住宅のニーズが増えています。ただし、省エネ効果を生み出せる木造住宅等を建てる場合には、太陽光発電の設置などで建物の重量が重くなっているほか、開口部の数を減らすなど、建築における制約が出てきます。
以上より、制約の条件をクリアし現代のニーズに合う木造住宅・建築物を建てられるよう、2025年4月から新たに2階建て以下の木造住宅・建築物の構造基準が改正されました。
住宅の原則ZEH化が定められている
前述した環境対策のために実施されている住宅のZEH化も、構造基準を見直す理由のひとつです。
利用する電力を住宅内でまかなう仕組みであるZEHを実現するためには、屋根に太陽光発電システムといった重量物を設置しなければなりません。その影響もあり、従来の構造基準では、壁量や柱の小径を計算できなくなりました。
そのため、2025年4月からスタートする新築住宅のZEH化に合わせ、建築企業がスムーズに設計できるように構造基準が改正されたのです。
まとめ
2025年4月より施行予定の「構造基準の見直し」により、壁量や柱の小径の計算内容が変化します。また改正によって、従来の設計検討の流れが変化する点に注意が必要です。
公益財団法人 日本住宅・木材技術センターから専用の設計計算ツールが提供されているため、小規模な木造住宅・建築物を設計する人は早めにツールの使い方を覚えておくのがよいでしょう。

